司書は、図書館における専門職として、本や情報を通じて社会や個人の知識向上を支援する重要な役割を担っています。
そんな司書になるためには、「司書資格」を取得する必要があるのです。
本記事では、司書試験の概要、取得方法、難易度、合格率、司書としての年収やキャリアについて詳しく解説します。
司書とは?
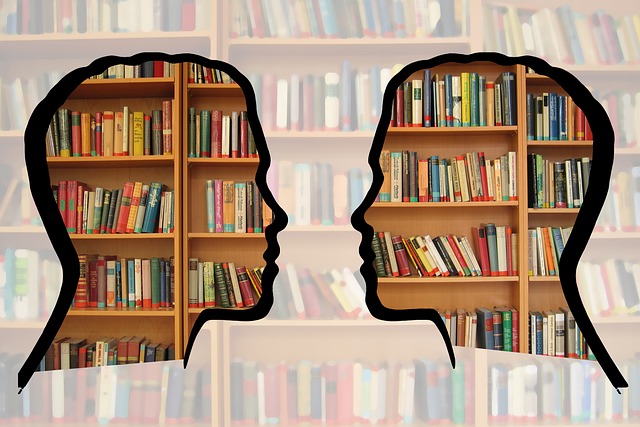
司書とは、図書館における専門的な職務を担う資格を持った職員を指します。
本や情報を通じて利用者の知識向上や文化活動を支援する重要な役割を果たします。
図書館の運営や利用者対応など幅広い業務を担当しており、単なる「本の管理人」ではなく、現代社会において情報の中核を担う存在です。
以下では、司書の具体的な役割をそれぞれ詳しく解説します。
資料の選定・収集・整理
司書の基本的な役割の一つが、図書館の蔵書管理です。
図書や雑誌だけでなく、近年では電子書籍やデータベースなどの電子資料も含めて、利用者のニーズに合った資料を選定・収集します。
さらに、収集した資料を日本十進分類法(NDC)などの分類法に基づき整理し、利用者がスムーズに資料にアクセスできるようにします。
また、古くなった資料の廃棄や、人気の資料の増刷対応など、蔵書の更新も重要な仕事です。
司書は、単に本を揃えるだけでなく、利用者が求める情報を的確に提供するための「情報空間」を構築する専門家と言えます。
利用者へのサポート(レファレンスサービス)
利用者が図書館を訪れる目的は様々で、読書を楽しむ人もいれば、特定の情報を探している人もいます。
その際に、利用者の質問に対応し、適切な資料を案内する業務を「レファレンスサービス」と呼びます。
例えば、学校の課題に必要な資料を探す学生や、地域の歴史について調べる研究者などに対して、司書は資料を探し出して提供するのです。
また、資料の使い方や図書館のシステムの説明なども行い、利用者が快適に図書館を活用できるようサポートします。
このように、司書は利用者のニーズを汲み取り、的確に対応する「情報の案内人」としての役割を果たします。
イベントの企画・運営
司書の仕事は資料管理や利用者対応だけにとどまりません。
図書館の利用促進や地域との交流を目的に、様々なイベントを企画・運営することも重要な役割です。
例えば、子ども向けの読み聞かせイベントや、地域住民を対象とした読書会、著名な作家を招いた講演会など、多岐にわたる活動を行います。
これらのイベントは、図書館が単なる「本を借りる場所」ではなく、地域の文化拠点として機能するための重要な要素です。
また、これらのイベントを通じて新たな利用者層を開拓することもできます。
司書には、イベント運営の企画力や実行力が求められる場面も多いのです。
図書館運営全般
図書館が円滑に運営されるためには、蔵書の管理やシステム運営、予算管理、職員の調整など、多岐にわたる業務が必要です。
これらの図書館運営全般も司書の重要な仕事の一つです。
特に、近年では図書館システムのデジタル化が進んでおり、電子資料の管理やデータベースの整備、オンラインカタログ(OPAC)の更新など、ITスキルが欠かせません。
また、施設の予算配分や運営方針の検討にも携わるため、管理能力やリーダーシップが求められることもあります。
司書は、図書館という公共施設を効率的に運営し、利用者にとって使いやすい環境を整える役割を担っています。
司書資格を取得する方法

司書として働くには、まず「司書資格」を取得する必要があります。
この資格は、文部科学省が定めた要件を満たすことで取得できるのです。
資格取得の方法は、主に以下の2つに分かれています。
それぞれの特徴や詳細を見ていきましょう。
大学や短大で資格を取得する
司書資格は、大学や短期大学で指定された科目を履修することで取得できます。
これは、教育職員免許状と似た仕組みで、大学在学中に必要な単位を取得して卒業することで、自動的に資格が付与される形式です。
文部科学省が定めた司書資格の必修科目には以下のようなものがあります。
- 図書館概論
- 図書館サービス論
- 図書館情報資源論
- 図書館情報技術論
- 図書館運営論 など
これらの科目では、図書館の役割や運営、資料整理の方法、情報技術の活用法など、司書に必要な基礎知識を学びます。
文系学部を中心に多くの大学で開講されており、学部の専門授業と並行して履修することが可能です。
大学での履修は在学中に資格取得を目指す学生にとって効率的な方法であり、特に新卒で司書を目指す人に適しています。
司書講習を受ける
大学をすでに卒業している方や、社会人として別の分野で働いている方でも、司書資格を取得することができます。
その方法が、夏季に実施される「司書講習」です。
司書講習は、大学や専門機関で行われる約3か月間の集中講義で、短期間で効率的に司書の知識を学べるプログラムです。
講習では、大学で履修する科目と同様の内容を学びます。
特に、社会人向けに設計されているため、実務経験を持つ受講者にも配慮されたカリキュラムが組まれているのです。
講習の実施期間は基本的に夏季休暇中で、平日昼間を中心に開催されることが多いですが、一部ではオンライン形式や夜間講義を提供している場合もあります。
この方法は、働きながら司書資格を取得したい人や、キャリアチェンジを目指す人に適した選択肢です。
どちらの方法を選ぶべきか?
大学在学中か社会人かによって、どちらの方法を選ぶかが異なります。
在学中であれば、大学や短大での資格取得が最も自然な選択肢です。
一方、大学を卒業してから司書を目指す場合は、司書講習を活用するのが現実的。
また、司書講習は短期間で資格取得が可能なため、時間を有効活用したい社会人にとって非常に便利な制度です。
それぞれの状況に応じた方法を選び、司書資格取得に向けて着実に進みましょう。
司書試験とは?

司書資格を取得するための試験や、資格取得後に図書館で働くための試験について解説します。
司書資格取得時には直接的な「司書試験」というものは存在しませんが、公務員として図書館で働く場合は、自治体が実施する試験に合格する必要があります。
それぞれの試験について詳しく見ていきましょう。
試験の概要
司書資格を取得する際には、大学での必要科目の修了や司書講習の修了が求められます。
これらの科目や講習では、最後に試験が課される場合があり、その合格が資格取得の条件となります。
ただし、これらの試験は比較的難易度が低く、必要な知識を学べば合格が可能です。
一方で、資格取得後に自治体の図書館で働きたい場合は、自治体が実施する公務員試験を受ける必要があります。
この試験では一般教養に加え、図書館業務に関連する専門知識が問われる場合もあるのです。
図書館専門職としての採用試験は自治体ごとに内容が異なり、面接や集団討論などの選考過程が含まれることもあります。
図書館学の基礎知識
公務員試験で図書館専門職を受験する場合、図書館学に関する基礎知識が試験科目となることがあります。
具体的には、図書館の役割や歴史、法律(図書館法や著作権法など)に関する内容が問われます。
これらは図書館の運営に必要な基本的な知識であり、司書として働くうえで欠かせません。
また、図書館の利用促進や地域社会との関わりといったテーマについても出題されることがあります。
これらの内容は、司書講習や大学での履修科目で学べるため、試験対策として復習しておくことが重要です。
基礎知識が問われる問題は暗記だけでなく、図書館業務の実際をイメージしながら回答できる力が求められます。
レファレンスと情報検索
図書館専門職の試験では、利用者の支援や資料の提供に関する知識が求められます。
特に、利用者の質問に応じて適切な資料を案内する「レファレンスサービス」に関する問題や、効率的な情報検索の方法について出題されることがあるのです。
例えば、「特定の分野の資料を探す際にどの分類法を用いるか」や、「利用者からの質問にどう対応するか」といった実践的な内容が問われる場合もあります。
また、データベースや電子資料の活用方法、ウェブ検索のスキルについても試験範囲に含まれることが多いです。
これらは実務でも非常に重要なスキルのため、試験対策としてしっかり準備しておく必要があります。
図書館運営
図書館の運営に関する知識も試験で重要なポイントです。
具体的には、資料の分類法(日本十進分類法:NDC)や、蔵書の管理方法、貸出システムの運営に関する問題が出題されることがあります。
これらは、図書館の業務を円滑に進めるために必須の知識であり、司書講習や実務経験で学ぶ内容です。
また、図書館の運営に必要な予算管理や利用者サービスの改善策に関するテーマが出題されることもあります。
これらの問題は単なる暗記ではなく、実際の図書館業務をイメージしながら回答する力が求められるため、過去問や模擬問題を活用して実践的な対策を行うことが重要です。
一般教養の試験
公務員試験では、図書館専門職であっても一般教養の試験が課される場合が多くあります。
この部分では、文章理解、数的処理、社会科学、自然科学、時事問題など、幅広い分野の知識が問われるのです。
特に、文章理解や時事問題は、図書館業務とも関連性が高く、利用者とのコミュニケーションに役立つ知識として重要視されます。
一般教養の試験は、公務員試験対策の基本書や問題集を活用して学ぶことが効果的です。
司書としての専門知識だけでなく、幅広い教養を身につけることが、公務員試験の合格につながります。
また、面接や集団討論での発言にも役立つため、日頃からニュースや社会問題に関心を持つことが大切です。
司書試験の難易度と合格率

司書資格を取得する難易度や、公務員試験で図書館職員として採用される際の難易度は、それぞれの条件や試験内容によって異なります。
大学や司書講習で資格を取得する場合は比較的ハードルが低いと言えますが、公務員試験では採用枠の少なさから競争が激しくなることがあります。
以下、それぞれの難易度について詳しく見ていきましょう。
司書資格の取得難易度
大学や短期大学で司書資格を取得する場合、指定された必要科目を履修し単位を取得することで資格が付与されます。
これらの科目は通常の大学の講義と同じ形式で行われるため、特別に難易度が高いわけではありません。
ただし、図書館学や情報管理に関する専門知識を扱うため、授業内容をしっかりと理解し、試験で成果を出すことが求められます。
一方で、司書講習を受けて資格を取得する場合は、社会人が短期間で集中的に学ぶため、時間の確保が課題となる場合があります。
講習の内容は充実しており、カリキュラムに沿って勉強すれば修了試験に合格できるよう設計されていますが、仕事や家庭と両立しながら取り組む場合には、計画的な学習が重要です。
公務員試験の難易度
自治体の公務員試験で図書館専門職を目指す場合、その難易度は高くなります。
特に地方自治体では、図書館職員の採用枠が非常に少ないことが一般的です。
採用人数が1~3名程度に限られることが多く、競争率が10倍以上となる場合も少なくありません。
このように、採用枠の狭さが難易度を押し上げる大きな要因となっています。
さらに、公務員試験では図書館学だけでなく、一般教養や時事問題など幅広い分野の知識が問われるのです。
文章理解や数的処理といった科目も含まれるため、司書としての専門試験だけでなく、総合的な学力が求められます。
特に図書館専門職を志望する場合、過去問を活用した徹底的な試験対策が必要です。
また、面接や集団討論など、筆記試験以外の試験にも対応する必要があります。
難易度を乗り越えるためのポイント
司書資格の取得や公務員試験の合格を目指すには、それぞれの試験の特性に合わせた対策が必要です。
大学や司書講習では、授業内容をしっかりと理解し、課題や試験に取り組むことが基本となります。
一方、公務員試験では、図書館学の専門知識に加え、一般教養や時事問題を幅広く学ぶことが合格への鍵です。
特に競争率の高い試験では、効率的な学習方法と計画的なスケジュール管理が重要です。
司書の年収とキャリア

司書としての年収やキャリアは、勤務先や雇用形態によって大きく異なります。
公務員として働く場合は安定した収入が期待できますが、契約職員や民間企業での勤務では条件が多様です。
また、キャリアパスも図書館内にとどまらず、専門図書館や民間企業など幅広い選択肢があります。
それぞれについて詳しく解説します。
公務員として働く場合の年収
地方自治体に図書館司書として採用された場合、給与は公務員の給与規定に従います。
新卒採用であれば、年収はおおよそ300万~400万円が一般的です。公務員の場合、勤務年数に応じて昇給があるため、経験を積むことで収入はさらに増加していくのです。
管理職に昇進すれば、年収500万~700万円程度になることもあります。
公務員としての司書の魅力は、安定した雇用と福利厚生にあります。ただし、採用枠が限られているため、競争率が高いことが課題です。
契約職員や派遣社員としての年収
契約職員や派遣社員として図書館で働く場合、年収は200万~300万円程度が一般的です。
非正規雇用のため、公務員のような昇給や福利厚生は期待できない場合が多く、雇用の安定性が課題となります。
一方で、契約職員や派遣社員は採用のハードルが比較的低いため、社会人として新たに司書を目指す人や、短期間で働きたい人にとっては現実的な選択肢となるのです。
また、図書館業務の経験を積むことで、正規雇用や他のキャリアへのステップアップに繋がる可能性もあります。
民間企業や学校法人の図書館での年収
大学や企業の図書館で働く場合、年収は勤務先の規模や雇用形態によって異なります。
大手企業や有名大学の図書館であれば、年収400万~600万円程度が期待できますが、中小規模の図書館ではこれより低くなる場合もあります。
特に大学図書館では、資料研究やデジタルアーカイブの運用など高度な業務が求められるため、専門スキルを持つ司書にとってはやりがいのある環境です。
民間企業の図書館では、ビジネスに直結する情報管理を行うケースが多く、司書のスキルをさらに発展させることが可能です。
専門図書館でのキャリア
医療、法律、ビジネスなど特定の分野に特化した専門図書館で働くことは、司書としてのスキルを深める良い機会です。
専門図書館では、その分野に関連する専門知識が求められるため、スキルアップにつながります。
また、専門性が高い分、図書館業務だけでなく、資料の分析や情報提供に特化した仕事が多く、キャリアの幅を広げることができるでしょう。
専門図書館での経験は、他の図書館や関連職種への転職時にも有利に働くことがあります。
学校司書としてのキャリア
小学校、中学校、高校の図書館で働く学校司書は、児童や生徒の読書活動を支援する重要な役割を担います。
単に本を貸し出すだけでなく、読書啓発のためのイベントや授業と連携した資料提供を行うこともあります。
学校図書館は教育現場の一部として機能しているため、生徒の成長を間近で支えられる点が大きなやりがいです。
学校司書は正規職員以外にも臨時採用が多い傾向にあるため、教育現場に関心のある人に向いているキャリアです。
研究職や大学職員としてのキャリア
司書としての経験を活かし、大学図書館で働くこともキャリアの一つです。
大学図書館では、学術論文や専門書の管理、研究者や学生への支援など、高度な知識やスキルが求められる場面が多くあります。
また、デジタルアーカイブや電子ジャーナルの運用に携わることもあり、情報技術に関するスキルを活かすことができるでしょう。
研究図書館で働く経験は、資料管理や学術支援の専門家としてキャリアをさらに発展させる機会となります。
民間企業での情報管理職への転職
司書のスキルを応用し、企業の情報管理部門で働く道もあります。
企業での情報管理職では、文書や資料のアーカイブ業務、データベースの運用、社内資料の効率的な管理などが主な業務となります。
特に、司書として培った分類・検索スキルや情報整理能力が活かされる場面が多く、図書館以外の分野でも活躍の場が広がるのです。
近年では、ITやデータ管理スキルを活用した「デジタルアーキビスト」としての需要も増えており、情報管理のプロフェッショナルとして新たなキャリアを築くことができます。
司書の魅力と課題

司書は、本や情報を扱いながら地域社会や個人に貢献できる魅力的な職業です。
一方で、雇用形態や技術の変化に伴う課題も存在します。
以下では、司書として働く魅力と、その裏に潜む課題について詳しく解説します。
読書好きにとって理想的な環境
司書の魅力の一つは、本や資料に囲まれた環境で働けることです。
日々、多様なジャンルの本や情報に触れることができるため、読書や知識習得が好きな人にとって理想的な職場と言えます。
また、最新の出版物や専門書を扱う機会も多く、読書の幅を広げたり、知的好奇心を満たすことができるのです。
さらに、利用者の興味や要望に応じて本を選び提供する仕事は、読書文化を支える喜びを感じられる場面でもあります。
こうした点から、司書は「本が好き」「知識を広げたい」という人にとって非常に魅力的な職業です。
社会貢献性の高さ
図書館は地域社会の知識や文化の拠点として重要な役割を果たしています。
その中心で働く司書は、地域住民にとって身近な「情報の案内人」として社会に貢献できる点が魅力です。
例えば、子どもたちの読書活動を支援したり、高齢者や障がい者向けサービスを提供するなど、幅広い年代や背景の人々を支える仕事ができます。
また、地域に根ざした図書館イベントを企画し、住民同士の交流を促進することも司書の重要な役割です。
こうした社会的意義の高い仕事に携われることは、大きなやりがいにつながります。
安定した職業
公務員として働く場合、司書は安定した雇用環境を得られる職業です。
地方自治体に採用されると、給与や福利厚生は公務員規定に基づくため、経済的な安定が確保されます。
また、正規職員として採用されれば長期的なキャリアを築くことが可能であり、退職金や年金などの制度も充実しています。
さらに、図書館業務は地域社会に根ざした仕事であるため、突発的な変化が少なく、安定した職場環境が整っている点も魅力です。
安定性を重視したい人にとって、司書は安心して働ける職業の一つと言えます。
雇用の不安定さ
一方で、契約職員や派遣社員として働く場合、雇用の安定性が課題となることがあります。
非正規雇用では契約期間が限られる場合が多く、更新が保証されないことも。
また、給与や昇給の面で公務員や正規職員よりも条件が劣ることが多く、長期的なキャリア設計が難しい場合があります。
こうした非正規雇用の割合が高い図書館の現状は、司書を目指す人にとっての大きな課題です。
安定した雇用を望む場合は、公務員試験に合格するなどして正規職員を目指すことが重要です。
限られた昇進機会
公務員として働く司書は、昇進の幅が限られていることが課題です。
図書館業務は専門職であるため、昇進しても図書館内の管理職にとどまることが多く、他の行政部門への異動やさらなるキャリアアップの機会が少ない場合があります。
また、地方自治体の規模によっては管理職のポストが少なく、昇進競争が厳しいこともあるでしょう。
このように、司書としてのキャリアは安定性がある一方で、昇進や収入増加の可能性が限られているため、キャリアの選択肢に制約がある点がデメリットとして挙げられます。
情報技術への対応
図書館業務は近年、デジタル化やIT化が進んでおり、司書にも新しいスキルが求められるようになっています。
例えば、電子書籍やデータベースの管理、オンラインカタログ(OPAC)の運用、デジタルアーカイブの構築など、従来の図書館業務とは異なる技術的な知識が必要です。
また、利用者からのデジタル関連の問い合わせに対応するため、ICT(情報通信技術)のスキルが欠かせません。
これらの変化に対応するため、司書は日々学び続ける姿勢が求められる点が課題となっています。
まとめ
司書は、本や情報を通じて人々の知識や文化を支える重要な職業です。
資格取得や公務員試験の難易度は決して低くありませんが、やりがいのある仕事として多くの人に支持されています。
年収やキャリアも勤務先や雇用形態によって異なるため、自分の目指す働き方を明確にすることが重要です。
司書を目指す方は、まず資格取得や試験対策に取り組みつつ、図書館業務の魅力を深く理解することをおすすめします。
ぜひ、この情報を参考に、司書への第一歩を踏み出してください。
